こんにちは!この記事では、「大学生協が勧めるパソコンって、本当に買うべき?」という悩みを持つ新大学生のみなさんに向けて、生協パソコンのメリット・デメリット、そして買うべき人・そうでない人の違いをわかりやすく解説します。
春から大学生活が始まり、新生活の準備に追われる中で、パソコン選びは意外と大きな決断ですよね。
特に、大学から届く入学準備資料の中に「生協パソコンのご案内」があると、「これって買わないとダメなの?」と不安になる方も多いと思います。
私の経験と生協パソコンを使っている友人からの情報を基に述べます!!
結論から言えば、生協パソコンは「安心を買いたい人」にはおすすめ。
でも、コスパ重視や機能重視の人には、他の選択肢も十分アリです。
それでは、具体的に見ていきましょう
生協パソコンとは?
まずは「生協パソコンって何?」というところから。
生協パソコンとは、大学生活協同組合(生協)が提携メーカーと共同で構成した、大学生活に特化したノートパソコンのことです。主にPanasonic、NEC、富士通などの国産メーカー製が多く、スペックやサポート体制も、大学の授業や課題提出に適した内容になっています。
大学によっては、**パソコン必携(持っていないと履修できない授業がある)**という方針をとっている場合もあり、そうした大学では生協パソコンの購入が強く推奨されるケースもあります。
生協パソコンのメリット
1. 安心のサポート体制
最大の特徴はこれ。保証期間が長く、学内にサポート窓口があるという安心感は他にはありません。通常のメーカー保証が1年なのに対して、生協パソコンは4年間の保証+過失による破損もカバーしてくれる「PCあんしんサポート」などが付属していることが多いです。
大学内に修理受付窓口があり、何かトラブルが起きたときもすぐに対応してもらえるのは、ITに詳しくない新入生にとって大きな安心材料です。
2. 授業・課題に対応したスペック
大学が独自に求めるスペック(CPU、メモリ、Office搭載、セキュリティソフト)にあらかじめ合わせて構成されているため、「買ったけどスペックが足りなかった…」という失敗が起きにくいのがメリットです。
また、Officeソフト(Word, Excel, PowerPoint)は最初からインストール済みというのも初期設定の手間を短縮できるので便利です。
3. 同期の多くが持っている
大学によっては同期の半数以上が生協パソコンを購入している場合もあります。周囲と同じ機種なら、トラブル時も「誰かが助けてくれる」確率が高いです。
個人的な経験なのですが、周りでは生協でのパソコンを使っている人が一定数居るので分からないことがあったら同じパソコンを持っている友達同士で相談することが出来ます。これは正直、サポート窓口以上のメリットだと思います。
パソコンを使うのが初めて、ないしは慣れてない人は何かと分からない事が多いと思います。その時に友達と相談できる強みは大きいと思います。また理系大学生ではプログラミングの環境構築でもしかしたら苦戦する事になる可能性もあるでしょう。何か困った時に同じパソコンを使っているという強みを大きいです!
生協パソコンのデメリット
1. とにかく高い
多くの人が一番気になるのが「値段」。生協パソコンは20万〜25万円程度と、かなり高額です。
スペックだけ見れば、同等の機種を家電量販店やネット通販で買えば10万円前後で手に入る場合もあります。
「同じCPUとメモリなのに、倍以上するのはおかしくない?」と疑問に感じる方も多いのが現実です。
2. 機種が限られている
自分好みのパソコンを選べない点もネック。
たとえば、Apple製品が好きでMacBookを使いたい人にとっては、Windows機限定の生協パソコンは魅力が薄く感じるでしょう。もちろん、大学指定でWindowsが限定されていたらOSは選べませんが、自分好みのパソコンを使えないのはデメリットです。
3. スペック過剰 or 不足の可能性も
用途に対して「オーバースペック」になってしまうケースもあります。
たとえば、メール・レポート作成・Zoom授業程度しか使わない文系学生にとっては、ハイスペックCPU+16GBメモリは不要な場合も。
逆に、工学部や建築系、映像編集などを行う学科では、生協パソコンではスペック不足になることもあります。
生協パソコン[surface]が壊れた!?
これは完全なる私個人の経験なのですが、surfaceを使っている私の友人5人の内3人が何かしらで故障していました。それは、surfaceのパソコンの構造上的に段差のある講義室で落としやすくなってしまう事があるからです。大学によりますが教室によっては後ろになるにつれて黒板が見やすいように段々になっている場合があります。すると比較的に横に細い机となる形となります。そしてsurfaceのパソコンは折り畳んだ状態から支えを使ってパソコンを立てる形になるため机を占領するスペースはキーボードの部分だけの面積ではありません。自立させる接線が必要になります。つまりその立てかける部分が机からはみ出てしまったら机から落としてしまいかねないのです。初期の1年春の時期ではそこそこ落とす音が講義室に響くことがありました。故に結果的に故障の原因になってしまうのです。
立てる時に、普通のノートパソコンとは違って支えを必要とする構造故に落とす機会が多くなって壊れやすくなっている印象です。
こんな人は生協パソコンを買うべき!
- 初めてのパソコンで設定や管理に自信がない
- 保証や修理体制がしっかりしている方が安心
- 同じ機種を持つ人が多い方が心強い
- 大学で推奨されていることに不安を感じたくない
- 文系・教育系・法学系などで、汎用的な作業がメインになる予定
こんな人は市販パソコンでもOK!
- パソコンにある程度詳しく、自分で選びたい
- 価格を抑えつつ、コスパのいい機種を探したい
- Apple製品(MacBook)を使いたい
- 保証は自分で家電量販店などの延長プランに入ればOK
- デザイン・映像・プログラミングなどの専門作業が多い予定
結論:迷ったら「情報収集+比較」で決めよう!
生協パソコンには確かな安心感とサポート体制があります。ただし、その分、価格が高めです。
「安心を買う」か、「コスパで攻める」かはあなたの性格や学部、使い方によって変わります。
【まずはこれをチェックしよう!】
- 学部・学科が求める最低スペック(入学案内に記載あり)
- パソコン必携かどうか
- 授業で使用するアプリやツール(Windows必須?MacでもOK?)
- 自分のITリテラシー(設定やトラブルに対処できる?)
おわりに
大学生活におけるパソコンは、4年間の相棒になる存在です。
高い買い物だからこそ、周囲に流されるのではなく、「自分のスタイルに合った1台」をじっくり選ぶことが大切。
生協パソコンを買うのも正解。自分で探して買うのも正解。
大事なのは、「何となく」で決めず、自分で納得して選ぶことです。
ぜひこの記事を、迷っている誰かの参考にしてもらえたら嬉しいです。
また、生協パソコンが壊れた話について記事を書きました。
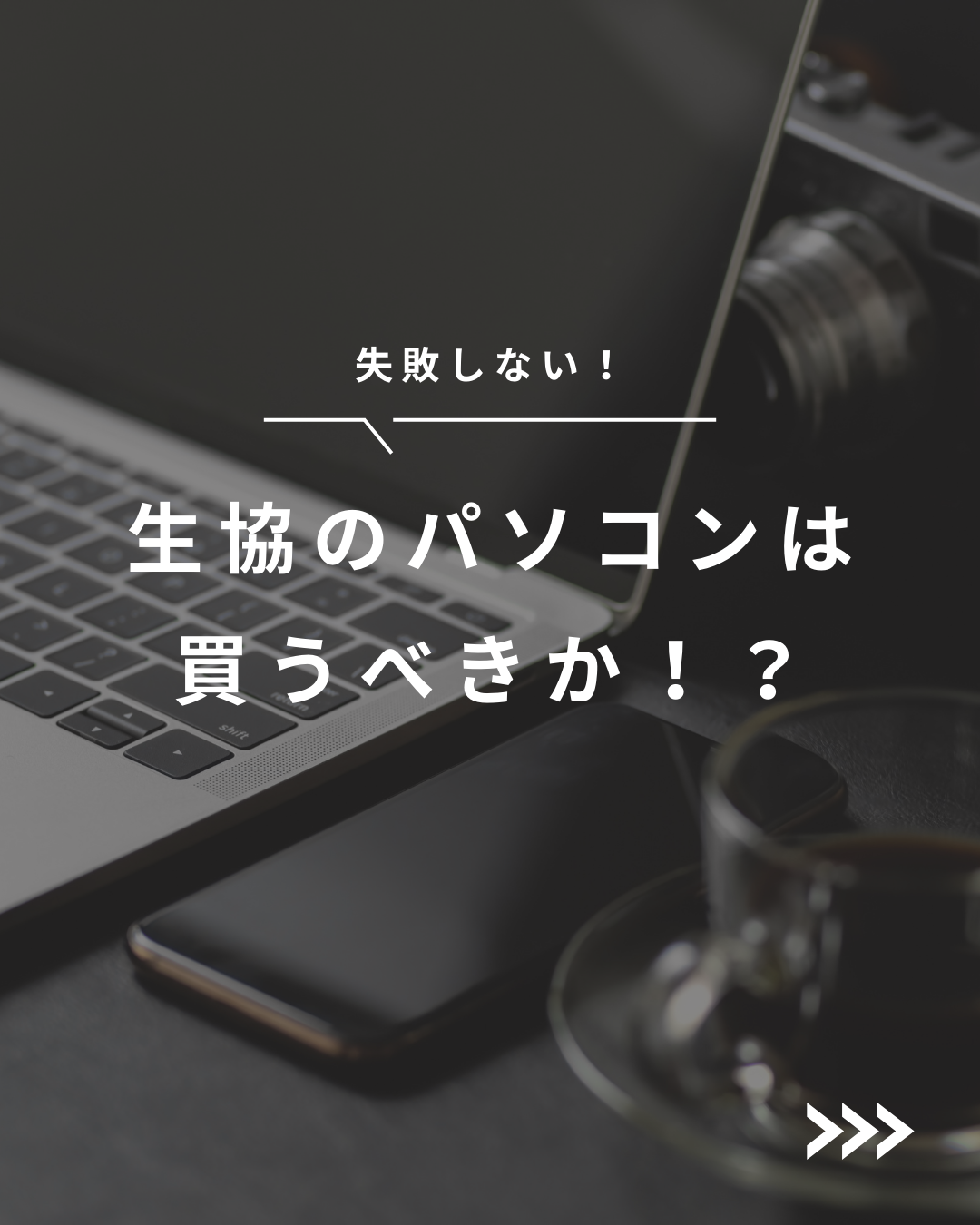



コメント