新学期が始まると同時に、大学ではサークルや部活動の「新歓(新入生歓迎)活動」が本格化します。限られた期間の中で、どれだけ多くの新入生に自分たちの団体の魅力を伝え、参加してもらえるかが、今後のサークル運営に大きく影響します。しかし、ただビラを配ったり、体験会を開くだけでは思うように人が集まらないことも多いもの。
では、「効果のある新歓活動」とは一体何なのでしょうか?この記事では、実際の大学サークルでの事例や心理的なポイントを交えながら、成功する新歓のコツについて考えていきます。
ちなみに私は実際に新歓活動を経験し今も実践している大学生です。実際の経験をもとにして何か少しでも皆様に有益な情報を与えられたら良いと思っています。
1. 新歓は「広報」と「体験」の二本柱
効果的な新歓活動には、大きく分けて「広報」と「体験」の2つの要素があります。どちらが欠けても、新入生の心は動きません。
広報:まず知ってもらうこと
どんなに素晴らしい活動をしていても、新入生に知られていなければ意味がありません。まずは、「このサークルって何をしてるの?」「どこにあるの?」という情報を、なるべく多くの新入生に届ける必要があります。
SNS運用
広報で最も効果があるものはSNS!!今の時代、大学の公式HPはおろかグーグル検索するより先にSNSを利用してサークルを探す人が多いでしょう。だからこそ、SNSを用いて新歓を行う事は最優先事項。加えてSNS運用は社会に出ても強力なスキルになる可能性もあります。自分自身の能力向上のためにもSNSを活用する事は重要になってくると思います。
X(旧Twitter)、Instagram、LINEオープンチャットなどを使い分けて、サークルの雰囲気やスケジュールを発信しましょう。ハイライト機能やストーリー、固定投稿を活用して情報を整理するのも有効です。
ここでSNSで最も大切な事はinformerである事。つまり、相手にとって有益な情報を与える事です。これは意外と難しい事です。自分が自分がと、己をアピールすること以上に新入生にとって欲しい情報を与える事が大切です。新入生が知りたい履修の情報や大学施設の紹介、周りの飲食店の情報などを発信しながらも自分自身のサークルについても軽く説明していく。自分が1年生だったころを思い出して知りたかった情報を与えることが重要になってきます。もちろん、それはサークルを紹介するときにも使えます。実際はあまり言いたくない部費事情だったり、用具の費用を公開する事も良い戦略になるかもしれません。
ここで各媒体でのおすすめの活用方法を紹介します。
まずはX(旧Twitter)
ここでは主に活動報告や内容説明をしましょう。出来る限りは部員でシフトを回して毎日投稿を心掛け、自分のサークルの情報をアピールしていき、認知をさせていきましょう。そして投稿する際は絶対に写真も付随させた方が良いです。文字情報メインの媒体だからこそ写真を載せることで目立たせることが出来ます。
次にInstagram
ここではリール、ストーリーをよく使い、そこから見てもらうことを意識しましょう。検索してプロフィールを直に見てもらうことは今や稀になってきています。普通の投稿も少し前に比べれば見られにくくなっています。ですので絶対に毎日ストーリーの枠を光らせておいて見てもらう様にしましょう。そして自分のサークルのプロフィールに飛んで見てもらったときに、そのサークルの詳しい情報や体験会案内が見れるように投稿をしておくと良いです。
そして公式LINE
公式LINEでは体験会の応募の際に利用させるのが良いでしょう。実際にやり取りする媒体はインスタやXよりも公式LINEの方が良いと個人的にはお勧めします。それはひとえに管理が楽だからです。インスタもXもDMでやり取りする事はあるでしょう。ですが、このバラバラにやり取りしている状態は非常に危険です。やり取りを取りこぼす事もあるでしょうし、実際に体験会の日になった時に何人参加するのか把握しづらいです。特に一人で管理するのではなくて複数人SNSを分担している団体ではなおさら最終的には1つに集約するべきです。
以上がSNS運用についてです。
その他の広報
- ビラ配り・立て看板:昔ながらの手法も侮れません。手渡しでのコミュニケーションは記憶に残りやすく、直接声をかけることで距離が縮まります。大学によってはビラ配りの時期があると思います。自大の新入生の人数を確認し、ビラを発注。そしてそのビラを部員でシフトを回し配りましょう。意外とビラを見て体験会に来てくれる子もいます。デジタルでなく、アナログの紙を手に持たせることは印象に残りやすいと思います。
- 生協や大学公式の媒体との連携:学内の掲示板や新入生向け冊子への掲載、生協の新歓イベント参加なども視野に入れましょう。特に新入生にとってサークル一覧は欲しがります。その一覧表に乗っていなかったら他サークルと比べて大きな損失です。公式サイトには必ず登録するようにしましょう。そして公式HPはあまり見られないと言っても、一定数見る人はいます。その人たちを取りこぼすのはとても惜しいという事で自分たちが出来る事は出来る限りやっておきましょう。
体験:実際に関わってもらう
サークルに興味を持ってもらったら、次は「実際に参加する場」を用意することが大切です。ここでは、「楽しそう」「この人たちとならやってみたい」と思わせる空気感が重要になります。
- 体験会・イベント:ただの説明会ではなく、新入生が主役になれる体験型のイベントを設計しましょう。初心者でも参加しやすく、「自分にもできそう」と思える工夫が鍵です。
- ごはん会・交流会:活動内容だけでなく、人間関係に惹かれて入る人も多いです。気軽な場を通して、「雰囲気が良かったから決めた」というケースを増やしましょう。特に一人暮らしの新入生にとっては無料の食事会は魅力的です。前面にアピールしてそもそも参加してもらえる母数を増やしましょう。
2. 「なぜ入るのか?」を逆算して設計する
新入生は、数え切れないほどのサークルに声をかけられます。その中から選ばれるためには、「どうしてそのサークルに入ろうと思うのか?」を逆算する視点が欠かせません。
よくある入会の決め手
- 楽しそうだった(雰囲気)
- 先輩が親切だった(人間関係)
- 活動が面白そうだった(内容)
- 自分のスケジュールに合っていた(頻度)
- 同じ学部や出身の人がいた(安心感)
このような「入る理由」を意識し、1つでも多く新入生に体感してもらえるような設計が、新歓を成功に導きます。そして自分のサークルを強みをアピールしていきましょう。
3. 新歓の「流れ」をデザインする
新歓は、単発のイベントではなく、「出会い→関心→体験→入会」の一連の流れをつくることが大切です。以下は、よくある成功パターンの一例です。
- SNSやビラで認知させる
- 少人数の交流会で関係性をつくる
- 体験会で活動の魅力を伝える
- LINEなどでリマインド・フォローアップ
- 入会説明会・歓迎会で意思決定を促す
この「関係性の深まり」に合わせて段階的に情報と体験を用意することで、自然な流れで入会までつなげることができます。
4. 大切なのは「数」より「密度」
新歓では「何人集まったか」が話題になりがちですが、本当に重要なのは「どれだけ深く関われたか」です。
たとえば、50人がチラッと説明を聞いて帰るよりも、10人がしっかり体験し、5人が熱心に質問をしてくれるほうが、実際の入会にはつながりやすいのです。
- 個別フォロー:LINEで一人ひとりに連絡してみる、質問があれば丁寧に答えるなど、細やかな対応が「このサークル、ちゃんと見てくれてる」という安心感につながります。公式LINEだけでなく個人LINEを交換し、やり取りをする方が重要です。注意が必要なのはその時に過度にメッセージを送ったり追いLINEなどをすると逆効果になりかねません。また、ラインを交換するときもなるべき同性同士で交換した方が特に女の子の新入生にとっては安心できるでしょう。
- リピーターを大切にする:2回、3回と来てくれた新入生は入会の可能性が高いです。名前を覚えたり、積極的に声をかけたりしましょう。
5. 最後は「楽しそうな先輩」で決まる
結局、新入生が見るのは「そのサークルにいる自分の姿」です。そのとき、目の前にいる先輩が楽しそうで、自分にもできそうで、何より人間的に魅力的に見えれば、「ここに入ろう」と思ってもらえる可能性が高まります。
- 無理にアピールしすぎない
- 自然体で楽しんでいる様子を見せる
- 新入生の話をよく聞く
- 圧をかけず、フラットに接する
このような姿勢が、安心感と信頼感につながり、結果的に良い新歓になります。
まとめ:効果のある新歓は「人と人をつなぐ設計」
効果のある新歓活動とは、一言で言えば「人と人とのつながりを丁寧につくるプロセス」です。
- よく練られた広報
- 誰でも楽しめる体験会
- 信頼を育むコミュニケーション
- 自然な流れでの入会までの導線
これらを意識して準備・運営することで、新入生にとっても先輩にとっても「よい出会い」になる新歓が実現できます。
もちろん、すべてが思い通りにいくとは限りません。でも、「目の前の一人に本気で向き合う」姿勢は、必ず誰かの心に届きます。
ぜひ、今年の新歓が実りあるものになるよう、チームで工夫を重ねていきましょう。


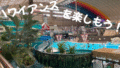
コメント