先日、今話題のお笑い芸人「令和ロマン」による苗字のコントを拝見しました。
私は、ほとんど渡辺みたいな苗字ですので山本とのコミュニティを作っていましたし、他の人よりも教室を俯瞰してみていたと思います。そこで日々思っていた苗字(出席番号)による子供への影響について考えをまとめてみました。
この記事の内容は多くを、出席番号が遅い私の記憶から書いています。経験からの記載ですので統計的に必ずしも正しいとは限らないです。
出席番号後半のメリット・デメリット
まず、出席番号が後半である事自体のメリット・デメリットについて考えてみましょう。
メリット
以下に番号を添えて羅列し、それぞれについて解説したいと思います。
- クラスメイトを観察できる→客観視
- 前の人の発言や発表内容を見聞きした上で自分の番を迎える→完成度を高められる。
- 先生から遠い→顔色を伺う事が少ない
- 相対的に発表の注目度が低め→低い緊張感
1,クラスメイトを観察できる→客観視
教室の一番後ろの席、また何かといって行事でも一番後ろに待機する事が多いので、クラス全体を客観的に見る癖が自然とついたと思います。教室で言うと、前の人に比べて全体を見ざるを得ないので、あの子は落ち着きがないとか、あの子は先生の話をよく気うタイプだという様に俯瞰する事が多かったです。
それは友達付き合いでも相手をよく理解してからコミュニケーションを行うことが出来るので友達付き合いに困ったことは人生で一度もありません。私だけでなく出席番号が遅い人で友達が全くいない人というのはそこまで見たことが無いような気がします。
2,前の人の発言や発表内容を見聞きした上で自分の番を迎える→完成度を高められる。
令和ロマンのネタでもありましたが、前の人の発言内容を聞いてから自分の番が回ってくるので比較的落ち着きがあり、内容もより練れてから発表することが出来ました。これは経験則ではありますが、明らかに違いが出来る事象だと思います。特に小学生低学年の感受性や成長速度において直前の失敗例や周りの反応を見て考えることが出来るのは非常にアドバンテージだと思います。
後にデメリットを書きますが、もちろん発表会などでは後半になると期待値が高まる事やオリジナリティが出せない様な可能性がありますがそれ以上のメリットだと思います。加えてたまにある出席番号逆順イベントのせいで咄嗟の対応力も鍛えられます。これは出席番号真ん中あたりの人には無いあるあるでしょう。
3,先生から遠い→顔色を伺う事が少ない
小学生にとって親以外の最も身近な大人は先生でしょう。人によっては先生こそが指針の様な人もいるでしょう。人格形成においての重要なピースです。その先生からの距離が遠ければ他の人よりも顔色を伺うことは少なくなるでしょう。また、普段の観察癖から先生が起こりそうなタイミングを計り、割と冷めた目で説教イベントをやり過ごすことになると思います。
4,相対的に発表の注目度が低め→低い緊張感
また何事にも最後に回されるので相対的に発表の注目度が低い事もあり、緊張が少ないです。少ない緊張感の中で発表を経験していきレベルアップするので割と発表が下手人が少ないと感じます。
メリット踏まえて
これらが渡邉(辺)強いてはその付近の苗字のメリットです。
デメリット
では反対に出席番号が遅い事によるデメリットは何でしょうか。
テストの採点が低くされる!?
まず最初に驚きの事実ですが、出席番号が遅い人の方がテストの点数が低く採点される傾向があります。アメリカのシカゴ大学の研究(2024年)において「面接やマッチングアプリでは、候補者の順番が後になるほど、否定的な評価になる」と報告され、さらにミシガン大学で行った成績の統計調査でも後半の人の採点の方が点数が低めに出ることが分かりました。
要するに採点される順番が遅い程、採点者の疲労や拘束時間等により低く採点されてしまうのです。
日本では多くが出席番号順に採点されるために後半の出席番号の人の方が成績が相対的に低めに出てしまう恐れがあり、これは大きなデメリットでしょう。

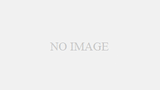
コメント
学生時代を振り返ると、前の子が先生にダメ出しされてるのをみて急いで自分の作品を修正したことがありました。もっとランダムに順番を決めないとダメですね。条件は公平であるべきです。
コメントありがとうございます。
よく発表では席順ではなくて出席番号順になることが多いですもんね。先生が成績を付けるのに楽なのでしょうが、公平にしてほしい瞬間もありますね。
ある意味平等なのかもしれませんし、仕方ない事の様にも思えます。